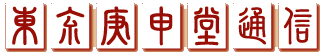
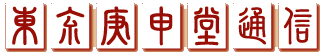
こんばんは。
満月の日の夕方に配信される読み物、
第二回目をお送りします。
前回お送りしたお話には予想外に多くの反響があり、
「ちゃんと書かなきゃな」と身がひきしまる思いでした。
およそ月一回の配信なので、三日坊主にはなりませんが、
三ヶ月坊主にならないよう、頑張ってまいります。
今日は庚申研究の第一人者、
窪徳忠先生についてのお話です。
蟲話02 「道教学者窪徳忠の気概」
◆ 庚申研究のバイブル
ぼくのようなド素人も含め、
庚申講について研究している人間が
まず間違いなくバイブルとしてとおる本が
「庚申信仰の研究」(窪徳忠・著/昭和36年刊)です。
膨大な資料渉猟と実地調査、そして緻密な論理構成で
いまだに他の追随を許さない大作なのですが、
それだけではなくこの本は、
いまではあたりまえとされている、
「庚申講のルーツは中国の道教である」
ことを証明してみせた本としても
大きな意義を持っています。
◆ 窪先生、庚申に出会う
この本の著者、窪徳忠先生は東大文学部東洋史学科の
出身で、もともと日本の民俗学者ではなく、
中国の道教の研究者でした。
ところが道教の資料を読みすすめるうち、
日本の庚申信仰と似たような記述が
頻繁に出てくることに気がつき、
しだいに日本の庚申信仰に興味を持ち始めました。
◆ 窪先生、柳田氏に出会う
窪先生は日本民俗学の大家である柳田國男氏のもとに
相談に行きました。柳田氏は庚申講について
すでに著作を出しており、そこでは
「日本古来の習俗であろう」と述べていました。
しかし柳田氏は、若い畑違いの研究者窪先生に対し、
笑って自分の所持する資料の閲覧を許しました。
◆ 窪先生、バッシングをうける
やがて窪先生は、集めた日本の資料と
自らの専門である中国道教の資料と重ね合わせて
「庚申講は中国の道教由来の信仰がもとである」
という説を学会で発表しました。
すると、民俗学者たちから激しい攻撃にあいました。
当時の日本民俗学会はみごとなまでに
「柳田原理主義」になっており、その神の結論に
異議を唱えることなど考えられなかったのです。
「民俗学のイロハも知らずに、何をたわけた空想を」
門外漢である窪先生は、さんざん嗤われそしられ、
学説は無視され続けました。
◆ 窪先生、牙をむく
窪先生がすごいのは、ここからです。
屈辱を感じた窪先生は、
じゃあ民俗学の手法で証明してやろう、と決意しました。
それまでのすべてを捨てて足掛け五年、
日本と中国の千を越す文献を渉猟し、
青森から鹿児島まで、五五一カ所におよぶ調査に
たった一人でおもむいたのです。
日本民俗学会にたてついた立場である以上、
そちらから大きなバックアップは得られなかった
ことは、想像に難くありません。
そんななか、ときには肺炎にかかり、
奥さんが制止するのを振り切ってまで、
雨の日も雪の日も、山を越え谷を渡って
実地調査を繰り返しました。
◆ 窪先生、勝利する
その苦労の末に完成した上下巻組の「庚申信仰の研究」は、
前述のとおり庚申講の成り立ちについての定説を
大きく塗りかえました。
本を読むと、窪先生の情熱と息づかいが感じられ、
そのころすでに衰退していた庚申講をテーマとしている
にもかかわらず、生の調査からくるリアルなドキドキが
随所にちりばめられています。
でも、本当のドキドキは、
最後の最後に待ちかまえていました。
◆ 窪先生とぼく
この本の奥付には著者の経歴とならんで、
著者の住所が書いてありました。
その住所は「東京都新宿区上落合3-24-15」。
なんとぼくの住むお堂と、歩いて五分と離れていない
ご近所にあったのです。
すごい偶然!
調べてみると、現在窪先生は隠居され
神奈川県に移られているようです。
しかし、窪先生が「素人のくせに」と嗤われ、
なにくそ、と頑張って研究していたときの本拠地が、
ぼくらの活動拠点であるお堂の目と鼻の先にあると知り、
ぼくはとても嬉しい気持ちになりました。
■
聴くところによると、窪先生はぼくら東京庚申堂の
存在や活動について、ご存知なんだそうです。
そこらへんについては、またいつか。
今日は天気が悪くて月がみえにくいようで残念。
次は、晴れるといいな。
次の満月は、六月三日です。
Copyright © 2001- Tokyo-Koshindo.All rights reserved.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||