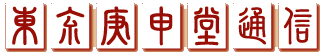
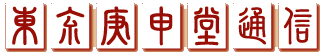
サルの手が長いのは、きっとあなたと握手したいから。
蟲話09 「サルが
◆ 庚申講とサル
庚申講には、いろんなところで「サル」が出てきます。
そもそも、庚申の「申」も「サル」ですし、
庚申塔や掛け軸には、「見ざる聞かざる言わざる」の
いわゆる三「猿」が多く見られます。
さらに、神道系の庚申の神様は「猿」田彦大神。
手を換え品を換え、いろんな形で「サル」尽くしです。
そこで今回、「サル」を中心に庚申講をみてみました。
すると、興味深い「サル」つながりが浮かんできました。
◆ 山王権現とサル
庚申信仰自体は特定の本尊を持たず、歴史的に
いろんな神さまが入れ替わってその座に着いた、
ということは、これまでの蟲話でも記したとおりです。
庚申講が日本に伝わって間もない室町時代には、主に
山王権現という神仏の融和した本尊が信仰されていました。
この山王権現というのはもちろん、
庚申講のためにつくられた神さまではありません。
ではなぜ、数多ある神さまたちのなかから、
山王権現が選ばれたのか。
じつはその神使(文字通り、神の使い。
お稲荷さんにおける狐みたいなもの)が、
「サル」だったのです。
庚「申」と山王権現がつなげられた大きな理由は、
ここにあったと考えられます。
◆ 青面金剛とサル
さて、時は下って江戸時代。
このころには山王権現の人気は衰え、
かわりに青面金剛という仏教の神さまが、
本尊として幅をきかせていきます。
神さまにも流行りすたりがあるのですね。
しかし、そこにもまた「サル」の姿が。
面白いことに、この政権交代が起こったあとも
「サル」は、そのまま神使として受け継がれてました。
主人は倒れても、家来のほうは生き残っている。
「サル」も案外、したたかです。
◆ 三猿で人気キャラクターに
ということで、江戸時代を中心として、
庚申塔や庚申の掛け軸に、「サル」がよく描かれました。
その多くにみられるのが、見ざる聞かざる言わざるの三猿。
この三猿は、またルーツの違うものなのですが、
三尸(人間の体内にいる三匹の蟲)の話や
「悪事を神さまに告げられないように」という目的と、
なんだかイメージが近いために、
モチーフとして採用されたのでしょう。
庚申といえば三猿というふうに、広く民間に浸透しました。
◆ 猿田彦とサル
そんな流れの中で、後れを取っていたのが神道系の宗派です。
これだけ巷で流行っている庚申講を、布教に活かさず、
ただ指をくわえて見ていてよいものか。
そこで神道由来の庚申講、というものがつくられ、
そのとき祀り上げられたのが「猿」田彦でした。
猿田彦は当時人気の神さまでしたし、「サル」つながりもある。
ということで、この人選、いや神選はぴったりだったのです。
◆ サルつながり
ということで、まとめると、
庚「申」講 → 山王権現の「サル」(神使)
→ 青面金剛に「サル」引継ぎ
→ 三「猿」(見ざる聞かざる言わざる)
→ 「猿」田彦大神
という大きな「サル」連鎖ができるわけです。
手足の長い「サル」たちが、庚申をモチーフにして
いろんな時代や宗派をつないでいる。
そう考えると、「サル」って案外すごいかも。
ううむ。
サル、あなどりがたし。
■
今日はもちろん、満月なのですけれど、
正確に言うと今夜ではなく、今朝の5時過ぎが月齢15でした。
月について書かれた本は数多く出版されていますが、
先月出たばかりの「月で遊ぶ」(中野純・著 アスペクト)
は、とくにお薦め。しちめんどくさい薀蓄本とは
一線を画す内容で、ひととおり知識のある月ファンにも、
月をいまいちど、新鮮に感じさせてくれます。
次の満月は、一二月二七日です。
Copyright © 2001- Tokyo-Koshindo.All rights reserved.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||